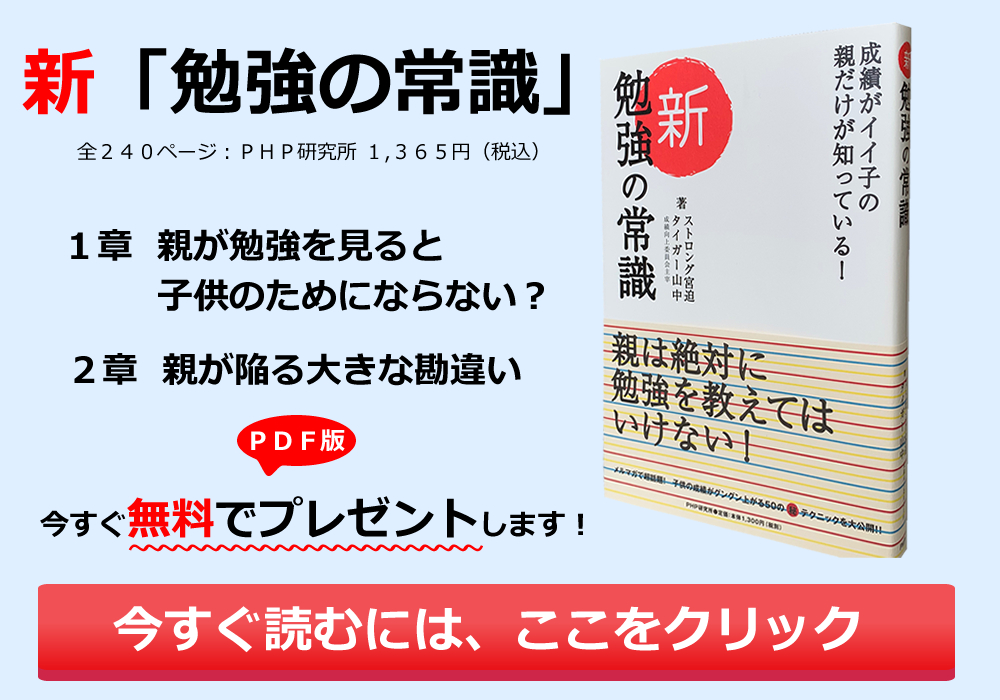ロバート・B・パーカーの探偵モノの本の中から1つ子供に関するものを紹介しましょう。
「ジェレドはいつもおとなしい子だった」彼女は言った。
「たぶん寂しかったのだと思う。わからないけれど。私はみんながいろいろなことに口を出しすぎるとずっと思っていた。
両親はつねに何か言おうとあの子のあとを追いかけていた。
どこへ行くの?
誰と行くの?
友だちは誰?
ガールフレンドはいるの?
大きくなったら何になりたい?私は自分の役割はあの子を休ませてやることだと思った。そこへ行けば、愛され尊重されていると感じられる場所、好きなだけ静かにしていられる場所を与えてやることだと」
「彼と長い時間いっしょにいたのですか」「とても長い時間」
「彼にガールフレンドはいましたか」私は言った。「知らないわ」夫人は言った。「友だちのことも、野心も、怖れも、希望も、夢も知らない」
「彼と何を話したのです」「本のこと、映画のこと、いろいな考え」
「考え?」私は言った。彼女は微笑んだ。「愛について話したわ。友情について。人はどうあるべきかについて。ひとりの人間が別の人間に何を負っているか、人を善良たらしめるのは何かについて」
ここではよく「あなたの子供が寂しがっていませんか」と書きます。そこで親は「友だちのこと、野心、怖れ、希望、夢」や勉強のことなど具体的なことについて子供から聞き出したり、追いかけたりする。
そうやって聞かれることがない子供にはそれもいいでしょう。しかし、なかにはそうしたことばかり聞かれる子供がいます。「みんながいろいろなことに口を出しすぎる」ってやつです。
「寂しさ」には誰からも相手にされない「寂しさ」があるけれど、いろんな人からいろんなことを聞かれ「すぎて」疎外感や寂しさを味わう場合もあります。特にお金には困っていない恵まれている環境にある子供にはよくみられる。子供からしたら、口出しはされるんだけど自分が困っていることは「聞かれない」って感じでしょうかね。
親や大人には当たり前のことも、子供には当たり前じゃないこともある。親や大人には小さな問題でも、子供には大きな問題なこともある。そうした齟齬に不満を持ちながらも、多くの子供たちは「爆発もせずに」社会に巣立っていきます。すばらしい。
→ 【お母さんからの相談】親が何かしてやれることはないだろうか?
もし爆発したら、こんなになるのかも・・・
そうした大人と子供の齟齬について、我が子について少しだけ考えるキッカケにこのパーカーの小説の一節がなってくれるとうれしいです。

「弟が」彼女は言った。
「それはもう絵に描いたような郊外の金持ち娘と結婚したの。ろくでもない女よ。でも可哀そうに、弟のほうが惚れてしまったから仕方がない。甥が三歳になると、彼女は有名私立校に入れようと心配しはじめた。その子は今、十五歳。有名校に入れるようにいい成績をとらなければと、たいへんなプレッシャーを感じているわ。有名校に入るには、課外活動でもいいとこを見せなければならない。クラスメイトにも人気がなければならない。つまり型どおりにふるまえってこと。正しい服を着て、正しい流行りことばを使い、正しい音楽を聴き、正しい休暇に出かける。正しい場所に住み、両親に正しい車を買わせ、正しい友だちとつき合って、正しい興味を持つ。宿題がある。サッカーの練習とギターのレッスンがある。何を、いつ、誰から学ぶべきかを学校が決める。どの階段をのぼるのかを学校が指示する。廊下をどのくらいの速さで歩くのか、いつ話してもよく、いつ話してはならないのか、みんな学校が教える。いつガムを噛んでいいのか、いつ昼食をとるか、なにを着ればいいか・・・・」
リタはことばを切って、マティーニを飲んだ。
「気の毒に」私は言った。「集団生活の準備方端だ」
彼女はうなずいた。「で、世のなかの人たちはみんな彼に、心配することがなくていいねえなんて言うわけ」彼女は言った。
「ところが本人は年から年じゅう心配してる。仲間に女々しいと思われてないか、いじめっ子に殴られるんじゃないか、女の子にかっこ悪いと思われてないかって」
「人生つらい時期だ」私は言った。
「いちばんつらい時期よ」彼女は言った。
「そうやって思春期をすごし、これからの新しい人格と必死で折り合いをつけようとしているあいだずっと、傷に塩をすり込むかのように大人たちの訳知り顔の笑みが向けられて、彼の苦悩をことごとく矮小化する」
「だがたしかに読み書き数字は習う」私は言った。
「習うわ。でもそれは早々に終わる。あとはほとんどごみよ。そして誰も彼の相談に乗ってやらない」
「きみは彼につき合ってやってるんだろう」
「数週間おきに【おばさん】をやってるわ。あの子がおぞましい郊外から列車に乗ってくるの。いっしょに博物館や店に行ったり、散歩して街を眺めたり。食事をする。話をする。夜はたいてい泊まっていって、朝、私が車で送っていくの」
「どんなことを話す?」
「がんばれと力づけるの」リタは言った。
今や彼女はいくぶん身を乗り出し、両手でテーブルを押さえていた。飲み物は無視されてぬるくなりかかっている。「おぞましい郊外が人生のすべてじゃないと言ってやる。あと数年でよくなるからと。無意味で、閉所恐怖症を引き起こしそうな人生の棺からすぐに出られる、四方の壁が崩れ、みずから動いて選べるようになる、タフでいられれば自分自身の人生を送れるようになるって」
話しながら、右手でテーブルを何度も軽く叩いた。「そのまえに爆発しなければ」彼女は言った。
「きみの最終弁論は迫力満点だろうな」私は言った。
彼女は笑い、椅子の背にもたれた。「あの子が大好きなの」彼女は言った。「しょっちゅうこのことを考えるわ」
「きみがいて彼は運がいい。世のなかには誰にも頼れない子が大勢いる」
リタはうなずいた。「彼を連れて逃げだしたいと思うことすらある」彼女は言った。
たった1人! 1人だけ我が子にこういう人がいてくれたらいいんですがね。
あなたのお子さんにはいますでしょうか、そういう人が?
物事を考える時、あれこれとひねくり回し出すと何が何だか、余計にわからなくなる事が多いですよね!何事も最初にふと思った事が意外に正解だったりします。そう思ったのなら、そう思う自分の感覚を信じるのも一つの手です。#俵越山 #越前屋俵太 pic.twitter.com/6cDE0ROt7p
— ほぼ毎日タワラの書 (@etsuzan_tawara) 2014, 8月 16